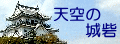
武蔵 腰越城

2017年の年明け、初登城となる城郭を埼玉県比企郡内六城を2週に掛けてめぐってまりりました。
今回は2週目第3弾、小川町にある腰越城です。
上の写真は二郭から本郭に至る虎口部分の写真となります。
powered by egmap.jp
腰越城は小川町・総合福祉センター/パトリアの駐車場をお借りしました。
この駐車場は施設と腰越城登山者両方の駐車場として小川町が運営しております。
お城への登城口は横断歩道のない県道を横切る形になるので注意が必要です。
県道を渡れば、大きな腰越城への登城口を示す看板が現れます(帰りにはパトリアへも!って書いてありますよ)。
登城前に見上げる小山が城跡(下1枚目)となり、時間はそんなに掛からないかなと思いましたが、そうは問屋が卸してくれません。
手作り感のある門を潜り(2枚目)イザ城へ向かいます。途中送電線鉄塔保安道への分かれ道が何本か分かれますが、総て左を選択してください。
しばらくすると(3枚目)の木段に繋がり、約15分ぐらいで(4枚目)の尾根に着くことが出来ますが、ご覧のような木段をあがるのに息が切れました。




現在の登城道は近年整備されたもので、実際は城・西側にある根古屋地区から本郭北側へのルート。
城・南側にある榎木戸地区から西郭南側へのルートがあり、後者のルートが大手道と考えられますが、現在は通ることが出来ません。*1
搦手口から尾根に上がった部分が、現在の登城口から登る尾根部分とで交錯します。 上の4枚目の写真がその場所にあたり正面の道が搦手口へ向かいます。
その尾根部分から本郭の容姿が目の前に現れますが(下1枚目)、本郭へ登るには巻道を通って大きく廻り込むことになり、暫く登ると、また下る(2枚目)と云ったトラップに嵌ります。
更に道なりに登ると、竪堀と思われる部分に階段が付けれら(3枚目)二の郭へあがることができます。築城当時、搦手からあがるときも現在の状況と同じだったのか微妙なところです。
二の郭からは腰廓・虎口を抜けて(4枚目)本郭にあがれます。




下の動画はスマートフォンで本郭から小川町方面を撮影したものになります。
初めてYouTubeへ投稿して、これで晴れて?YouTuberになりました。まぁHTMLに華を添えたくて、やってみた次第でぇ。
更に
下にある写真は、小川町に裾野を拡げる仙元山で、その右側にある峰が
青山城になります。

【歴史】「日本城郭大系」によると、歴史上に腰越城は名前が出てくるのは「小川町の『青木家譜』によれば治承四年(1180)、
山田伊勢守清義が宇治川の先陣に敗れた後、籠城(ろうきょ)するために築く。」*2 とされ、その後は山田家累代の居館となったといわれています。
戦国時代に入っても山田家は存続し、戦国末期には北条氏直に仕えた山田伊賀守直義の長男・直定(直昌)が
松山城主上田案独斎朝直の家臣として東松山にある青鳥城と、この腰越城を松山城の支城として任せられます。
しかし、赤坂の原合戦で道祖土図書助により討死したため、次男・直安が山田家の家督を相続。 北条家滅亡時にはここ腰越城を開城、のちに徳川家康から三百石を与えられ旗本に取り立てられました。




*1 :「日本城郭大系」によると、昭和の戦前に石灰岩の採掘場として西峰部分が削りとられてしまいます。採掘前は石灰岩の急峻な崖に覆われていたとのこと。
*2 : 『宇治川の先陣』に関わる故事は元暦元年(1184)宇治川の戦いで発生。年号が確かであれば治承四年(1180)に「以仁王の挙兵」が起きた宇治川近辺での戦陣を指しているのか。














