|

播磨 城山城址
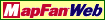

城山城 2000年8月27日
城山城(きのやまじょう)周辺は古墳が多く存在し、寺院もまた多くあり平安時代からその歴史があります。 この城の歴史も古く赤松則祐が文和元年(1352年)から20年掛けて築いた城とされています。 城山城の代表されるのが、1441年「嘉吉の乱」が有名です。 前期赤松家が足利幕府六代将軍足利義教を謀殺し、追討軍(山名氏・細川氏)に攻め滅ぼされた舞台がこの城山城です。 播磨の赤松家の衰退がここから始まる訳です。
この城山城を観て赤松家に興味が湧いてきました。 初めは赤松家の前期?・後期?と言われても何のことかサッパリ解らず、調べていくうちに播摩での赤松家の繁栄・衰退・復活・滅亡と200年以上にもわたり、色々な話があるだけに興味が湧いてきたものだと思います。
残念なことが写真を見ても判るとおり城山城に着いた時間が遅く、この山の頂上付近が城山城なのですが登ることが出来ませんでした。。。 |
|
 |
|
城山城の麓付近しか見て回れなかったのですが、兵糧道の入り口付近には赤松家一族の供養塔がありました。(木の茂った所にあり昼間でも暗いところで少し身震いしました)
左の写真は大手道の入り口付近です。この道の右側には古墳群が沢山ありましたし、入り口に至る道中にも現代のお墓がありました。 搦手道にも足を運んでみましたが、やはり現代のお墓を通り抜けると古墳群があるといった感じでした。 この城の経緯、近くに古墳あることを考えると、ちょっと背筋が凍りました。(地元の方すいません) |
|

|
|